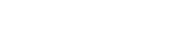【心游舎 書道ワークショップ 開催のご報告】
令和7年3月29日(土)
学問の神様として名高い北野天満宮に於いて、書道のワークショップが開催されました。
先ず、参加者全員で正式参拝の後、境内にある文道会館へ移動し開会となりました。
はじめに彬子女王殿下より、書道上達の為には出来る限り、筆を取り書に触れる機会を増やすことが大事であるとおことばをいただきました。
次に北野天満宮権宮司の神原孝至さんより楼門に掲げられている扁額『文道大祖風月本主』についての解説を交えて書道の意義と菅原道真公と関連した書の歴史についてご教示いただきました。文道大祖とは菅原道真公が学問・文学の祖であり、風月本主とは漢詩・和歌に精通していたことを意味しています。
神原さんのご講義ののち、書道の実技指導に入りました。講師は皆様お馴染みの優しくて褒め上手、みんな書道が好きになるご指導の神郡宇敬先生です。今回は2年ぶりの書道ワークショップの開催ということと、春休み期間も重なり、子どもから大人まで多くの方々がご参加されました。
先ず墨をすることからスタート。コツは余り力を入れ過ぎないことと「の」の字を書くように、または上下に墨を動かします。
次に揮毫する上での注意点として
1、筆をしっかり立てて書くこと。
2、手首を使わずに肘で線を引くこと。
3、筆はすべておろし、根本まで墨を含ませること。
この3点が重要とされ、これらのことを踏まえ半紙に丸やギザギザ模様を連続で書いたりしながら徐々に筆に慣れていきました。
先生にご用意いただいた『花吹雪』『桜』『新学期』など、春を感じるお手本と、楷・行・草書体で書かれた参加者一人一人の氏名をお手本に書いていきます。
参加者はお手本の中から文字を選び、半紙に向かい筆を走らせていました。
神郡先生は各テーブルを回られ、良い点を褒めながら、この点に気を付けると更に良くなるとアドバイスをされ、子どもたちは笑顔の中にも、少しでも上手に書きたいという思いで真剣に取り組んでいました。半紙に練習の後、清書として北野天満宮の書初め、天満書で使用される半紙に揮毫しました。時間が足りないという声も聞かれましたが、限られた時間の中で書道に没頭しそれぞれに納得できる作品を仕上げました。
神郡先生は職業柄、お子さんが生まれたときに命名書をお願いされることが多いそうです。しかしながら、父母が子どものことを思い書く書には両親の気持ちが宿り、書家でも敵わないという話は印象的でした。
最後にいただいた講評で神郡先生は『呪い』という文字を書かれ、何と読むか問いかけました。会場から「のろい」「まじない」の答えが出されました。
勿論、読み方はどちらも正解です。
「のろい」は誰かに対して悪意を抱く時に使い、一方、「まじない」は悪いものから身を守る時に使います。
文字が同じでも意味が異なり、用いる人の視点によって読み方、また書く時にはその文字への気持ちの入り方が変わるということでありました。書道や物事も一点から見つめるのではなく、さまざまな角度から見つめることで今までとは違った気づきがあることを教えていただきました。
継続は力なり!書に触れる機会を増やし、また来年、今年よりも上手く書けるように頑張りましょう。
次回は4月20日、東京の神田神社にて心游舎の総会と感謝の集いを開催します。
ワークショップでは彬子女王殿下、万九千神社の錦田剛志宮司、そして演出家の宮本亞門さんをゲストにお招きし、日本神話をテーマにしたトークセッションを開催いたします。是非、ご参加下さいませ。


















※写真の無断転載は固くお断りいたします。