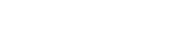装束の中に「袿(うちき)」というものがあります。これは「うち着るもの」、つまり「はおって着るもの」の意味からきた名称でございます。
平安時代、これを何枚も重ねて着るとき、下に着ている色目が見えるよう、上に着るものは少しずつ小さく仕立てます。
そうして、最も上に着るための袿はそれにふさわしく色や織、文様も贅沢なものが使われる一方、丈は他と比べて小振りの袿となります。これが「小袿(こうちき)」です。当時「小袿」は平安貴族が日常に着ている服でしたので「褻(け)の装束」と呼ばれました。これに対して十二単は儀式などに着られ、「晴れの装束」と呼ばれていました。なぜそのように呼ぶかというと、日々練習してきた大舞台を「晴れ舞台」と呼ぶように非日常を示す「ハレ」、その反対に日常を意味するのが「ケ」という言葉なのです。
鎌倉時代になると武家が政権を握り、貴族たちの経済力は急激に低下していきます。中国から伝わり日本独自の文化となった十二単などの装束も、この経済困窮によって危機に陥ります。宮中では日常の奉仕は袴に白小袖だけとなり、身分の低い人々は袴も着ずに小袖に薄衣と呼ばれるものを着て奉仕することとなりました。平安時代に流行った華麗で優美な服装への反動とあいまって、武家たちの極端な簡略化が始まるのです。
そうして十二単の下着的存在であった白小袖が、鎌倉時代に下着の小袖と上着の小袖とに分化してゆき、室町時代には身分ある武家の婦人たちは白色の下着の小袖の上に美しい織や色の上着の小袖を「打ち掛けて着る」ようになり、この「打掛」の姿を冬の礼装としました。
そうしてこの打ち掛けて着る小袖は、江戸時代にも引き続き武家夫人の礼装として着られ、現代でも見られる花嫁衣裳「ウチカケ」へと確立されていくのです。