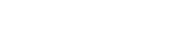三寒四温を繰り返しながら、春を迎えました。京都は桜が咲き始め、芽吹いた柳の葉が少しずつ大きくなっています。
「見わたせば 柳桜をこきまぜて みやこぞ春の錦なりける」
と『古今和歌集』で素性法師が詠んだような、桜の薄紅色と柳の優しい緑のかさなりが、まるで織物のように美しい、と思える自然の風景が広がっています。
色を言葉で表現するときに、赤、黄色、青と単純な名前もありますが、実は日本には、200種以上の色の名前があると言われています。
平安時代に暮らしていた方々は、季節の移りかわりにとても敏感で、その季節に咲く花や草木の色を表わすために、桃色、桜色、柳色、山吹色、藤色、紅葉色、などと名付けました。
なんとなく、花の色は想像がしやすいと思いますが、当時の人々は葉や草の緑にも細かく名前をつけています。
柳の葉の色のような淡い黄味がかった緑を「栁色」といいますが、柳の葉の裏を見てみると、表の葉に比べて少し白っぽい色をしています。そのような色を「裏葉色」と名付けており、注意深く植物そのものを観察し、色を使いこなしていることがわかります。
「山笑う」という言葉は、丁度今頃の季節の山の状況を表しています。山の木々は暖かくなるにつれ、次々と新しい芽が芽吹きはじめ、美しい新緑をたたえています。
それを「萌黄色」と名付け、地に映える草には「若草色」と名付けています。そして、田んぼに植え付ける苗には「若苗色」、筍が成長して伸びた竹には「若竹色」と続きます。その新緑はやがて少しずつ色を濃くしていきますが、それにも1つずつ名前を付けて、色が変わっていく様を楽しんでいたようです。
外に出る時間が少なくなっていると思いますが、もし山を見たり、道を歩いていて素敵な植物を見つけたら、自分の考えた色の名前をつけて、それをお家で絵の具や色鉛筆で表現してみてはいかがでしょうか?
ところで、葉の色が緑なので、それでそのまま染められるのではないか、と思ってしまいがちなのですが、実は葉の緑を形成している葉緑素はとても弱く、すぐ変色したり、水に流れてしまいます。美しい新緑の色を表わす時には、その葉を使って染めるのではなく、まず青の色素を持っている蓼藍で青く染め、その上に刈安や梔子など黄色の色素をもつ植物で染め重ねて緑にします。